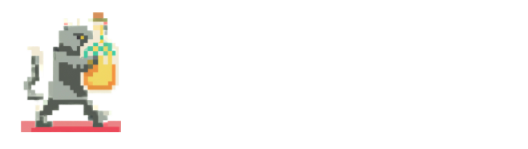引き続き「その食品は本当に栄養豊富なのか?」を考える方法を考える
かなり間が空いてしまいましたが、前回に引き続きカルシウムの話題です。入手や加工しやすいデータを活用して、手軽に食品の栄養をざっくりと理解する方法を考えていきたいと思います。
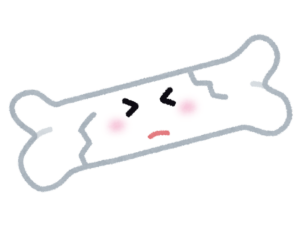
食品成分表と食事摂取基準
今回も日本食品標準成分表2020年版(八訂)(以降、食品成分表と呼ぶ)と日本人の食事摂取基準(2020年版)(以降、摂取基準と呼ぶ)を参照しながら食品のカルシウム量などについて見ていきます。
なお食品単体の栄養と、摂取基準に基づいた必要量についてはtowser’s labが提供している「食品の栄養を調べるアプリ」で簡単に調べることが出来ます。ver.1.2.0から新たに増補2023年に対応しましたので、ver.1.1.0以下をご利用の方も是非アップデートしてみて下さい。

主力級食品
200mg以上1000mg未満の食品は175項目。上限1000mgは成人の一日の推奨量600~800mgを余裕で超えており、ちょっと幅が広すぎたかも知れません。が、ここまで含めても食品成分表の7%であり、調味料などを除けばやはり選択肢は結構限られると言えるのではないでしょうか。
チート級食品、すごい食品はコストなどの理由から常用するのは難しいのでは?という食品が殆どでしたが、このレベルになるとお馴染みの食品が出始めます。
- 小魚
- 刻み昆布(940mg)、まあじ 小型 骨付き から揚げ(900mg)、ししゃも生干し 焼き(360mg)、いわし類缶詰 水煮(320mg)
- 野菜、海藻
- 削り昆布(650mg)、カットわかめ 乾(870mg)、モロヘイヤ 生(260mg)、水菜 生(210mg)
- 乳製品
- 全粉乳(890mg)、プロセスチーズ(630mg)、カマンベールチーズ(460mg)、モッツァレラチーズ(330mg)
- その他(豆類、加工品等)
- ハードビスケット(330mg)、がんもどき(270mg)、煎りアーモンド(260mg)
上位層だと100gで一日に必要な摂取量を超えますし、下位層でも半分~1/4程度満たせる量なので、十分魅力的な食品群かと思います。とは言え乾物など実質的に少量しか接種できないものもあるので考慮が必要です。例えば、乾燥わかめは素干しの乾燥状態だとカルシウム830mgもありますが、水戻しだと100mgです。一方、チーズ類は量もそこそこ食べられてこれだけの量は凄い。カルシウムといえば乳製品というイメージも伊達ではないようです。まぁカロリーも塩分も多いので毎日沢山食べるのは良くないと思いますが。
なお野菜についてはモロヘイヤと水菜くらいがかろうじてランクインというところです。カルシウムの多い野菜として紹介されることの多い小松菜 生は170mg、青梗菜 生が100mgとなっています。確かに日々の料理に使いやすい食材としては優秀ですが、前述の主力級食品と同列に語るのは誤解を招くのではないかなと思います。野菜に関しては、これらを食べたら即カルシウムが満たされるものはなく、他の食品との栄養バランスで複数組み合わせて考える必要がありますね・・・なんだか当たり障りのない結論になってしまいました(笑)。カルシウム足りてないなーという時は、主力級食品以上の食品を取るのが手っ取り早いかなと思います。
ちなみに日本人に関してはカルシウム源としての牛乳は望ましくないという話もたまに見聞きしますが、これは乳糖を含むため体質的に合わない人が割と多いということと、マグネシウムが少ないのでバランスに欠けるということが主な理由のようです。確かにこれらは考慮すべき事柄ではありますが、今まで見てきたようにカルシウムはとても貴重な栄養素なので、これだけで選択肢から外してしまうのは勿体ないと思います。これらを根拠に学校給食の牛乳をディスるのはどうかなと思います。
そもそもカルシウム不足は本当なのか
ここで今更な話ではあるのですが、カルシウム不足が本当に重要な問題なのかを考えたいと思います。そもそも「現代人が不足気味な栄養素の代表選手」ということでカルシウムを多く含む食品を見てきたのですが、実際はどうでしょうか。不足すると骨粗鬆症になってしまうとかイライラするとか良く聞きますが、本当にそうなのでしょうか。
食事摂取基準には以下の記載があります。
血液中のカルシウム濃度は、比較的狭い範囲(8.5〜10.4 mg/dL)に保たれており、濃度が低
日本人の食事摂取基準 より抜粋
下すると、副甲状腺ホルモンの分泌が増加し、主に骨からカルシウムが溶け出し、元の濃度に戻
る。したがって、副甲状腺ホルモンが高い状態が続くと、骨からのカルシウムの溶出が大きくな
り、骨の粗鬆化を引き起こすこととなる。骨は、吸収(骨からのカルシウムなどの溶出)と形成
(骨へのカルシウムなどの沈着)を常に繰り返しており、成長期には骨形成が骨吸収を上回り、骨
量は増加する。カルシウムの欠乏により、骨粗鬆症、高血圧、動脈硬化などを招くことがある。カ
ルシウムの過剰摂取によって、高カルシウム血症、高カルシウム尿症、軟組織の石灰化、泌尿器系
結石、前立腺がん、鉄や亜鉛の吸収障害、便秘などが生じる可能性がある。
骨からのカルシウムの溶出・・・こういう情報を見ると怖くなりますね。骨がスッカスカになっているイメージ。でも逆に見ると、これによって血中のカルシウム濃度が一定の範囲に保たれるので、イライラするといった神経系の話は違いそうですね。なお、ビタミンDが欠乏すると血中のカルシウム濃度が低下するそうです。
骨密度に関してはどうでしょうか。
カルシウム摂取量と骨量、骨密度、骨折との関係を検討した疫学研究をまとめたメタ・アナリシ
日本人の食事摂取基準より抜粋
スによると、摂取量と骨量、骨密度との間には多くの研究で有意な関連が認められている 53─55)。
カルシウム摂取量と骨折発生率との関連を検討した我が国で行われた疫学研究では、有意な関連
(摂取量が少ない集団での発生率の増加)が認められているが 56)、世界各地の研究をまとめたメ
タ・アナリシスでは、摂取量と発生率の間に意味のある関連は認められなかった 57)。このように、
疫学研究の結果は必ずしも一致していない。
うーん、なんだか微妙。骨量、骨密度との関係は認められるものの、それが骨折発生率に影響しているかは断言できないみたいですね。まぁ、気をつけるに越したことはないという感じですね。骨はカルシウムだけで出来ているわけではなく、他の栄養素の接種状況にも左右されるでしょうから難しいところではありますが、この辺については別途深掘りしていきたいです。
なお、現代の日本人がカルシウム不足気味なのかについては、摂取基準に該当する記載は見当たりませんでした。一方、摂取基準とは別の、学校給食摂取基準に関する報告書には以下の記載があります。
男子の栄養摂取状況を見ると、小学3・5年生及び中学2年生とも、食塩、脂質及び
学校給食摂取基準の策定について(報告)より抜粋
食物繊維について不適合率が高く、特に食塩については、すべての児童生徒が目標量
を超える量を摂取しているという結果となっている。また、ビタミン・ミネラルにつ
いては、中学2年生の不適合率が小学3・5年生と比べ全般的に高く、特にカルシウ
ムは、不適合率が 50%を超えている。一方、小学3・5年生は、ビタミンC、カルシ
ウム及び鉄を除き、不適合率は高くない。
カルシウム不足の子供は多いようです。これが何らかの病気に繋がっているかは分からない(この辺に言及する記載は見つからない)のですが、学校給食としてはこの現状を鑑み、カルシウムを多く含む献立になっているそうです。
(イ)カルシウム
学校給食摂取基準の策定について(報告)より抜粋
昼食必要摂取量の中央値は、食事摂取基準の推奨量の 50%を超えているが、献立
作成の実情に鑑み、四分位範囲内で、食事摂取基準の推奨量の 50%を学校給食の基
準値とした。
私達の知らないところで様々な配慮や努力がされており、それが日々の健康に寄与しているかも知れないということですね。有り難いことです。
サプリ
カルシウム不足による健康被害については結局良く分からないところもあるのですが、過剰摂取にならない範囲で多く取るに越したことはないというのがとりあえずの結論じゃないでしょうか。
必要量のカルシウムを日々の食事から接種するのが難しいとしたら、サプリはどうでしょうか。
以上から、2015 年版 4)と同様、不確実性因子を 1.2、最低健康障害発現量を 3,000 mg とし、
日本人の食事摂取基準 3-2-1 太陽上限料の策定方法
耐容上限量は 2,500 mg とした。日本人の通常の食品からの摂取でこの値を超えることは稀であ
るが、サプリメントなどを使用する場合に注意するべき値である。2008 年、2010 年にカルシウ
ムサプリメントの使用により、心血管疾患のリスクが上昇することが報告されている 98,99)。この
報告に対しては様々な議論がある 100)が、通常の食品ではなく、サプリメントやカルシウム剤の
形での摂取には注意する必要がある。また、ビタミン D との併用によっては、より少ない摂取量
でも血清カルシウムが高値を示すこともあり得る。
カルシウムに限らず摂取基準ではサプリはあまり良いように書いていないというか、取り過ぎに注意という記載が散見されます。そもそも、カロリー、糖質、脂質、ナトリウムあたりは別として、その他の栄養素は一般的な食品には過剰摂取になるほど多くは含まれていないのですよね(レバーのビタミンA、煮干しのカルシウムなど例外もありますが)。ただ、サプリの使用自体を否定している訳ではありません。
カルシウムと名前がついているサプリの含有成分としては炭酸カルシウムが多く、他にクエン酸カルシウムとハイドロキシアパタイトがあるようです。原材料については卵の殻や貝殻などが多く、分かりやすい栄養素と言えるのではないでしょうか。コストや摂取の手間を考えるとマグネシウムなどとセットになっているものが欲しくなりますが、安易に選ぶと過剰摂取になる可能性が高くなるので注意しましょう。
まとめ
- 小魚、乳製品、一部の海藻や豆類にカルシウムは多く含まれる。また、これらに比べると一段劣るが、野菜の中にもカルシウムを多く含むものが多少ある。
- 骨折発生率に影響しているかについてははっきりとした結論が出ていないものの、カルシウム不足と骨量、骨密度との関係は認められるため、やはり摂取量には気をつける方が良い。
- サプリの使用については取り過ぎに注意する必要がある。